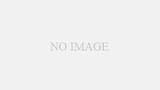割合の単元が小学生が算数が苦手になるかならないかのポイントとなるところです。5年生で割合が出てくると、苦手にするお子さんも多いと思います。しかし割合の考え方は日常生活で非常に大切になります。次のことを参考にして、日常の中で割合の感覚を身につけてみてください。
公式を覚えているだけでは割合は理解できない

割合の公式を丸暗記しているだけでは、しっかり理解出来ていない事が多く、難しい問題になると出来なくなってしまうケースが多くなります。
教科書に出てくる、「もとにする量」「くらべられる量」という概念を公式のように覚えてしまうと、問題が変わった時に、かけ算かわり算か分からなくなってしまう・・・という状態になってしまいます。これでは受験に出る応用問題や、中学の数学の文章題が解けなくなってしまうことになりかねません。
割合の学習のポイントはいろいろありますが、まずは日常生活の中から割合という概念を学んでみるようにしましょう。
ホールケーキやピザを分ける
簡単な割合の概念を学ぶ中で、下のようなホールケーキを分けることを考えてみます。
4人で同じ大きさで分けるなら、
1人分は分数で表すと 4分の1 これを小数で表すと 1÷4=0.25 →百分率で表すと25%になります。
つまり 割合でいうと、もとにする量=1 くらべる量=4 となります。
これを具体的な数字に変えてみます。
ケーキの重さが400g だとします。
1人分が25%なら、食べるケーキの重さは 400×0.25=100g という式で表せます。
また、1人分が25%で、重さを量ってみたら100g だったとします。
全体のケーキの重さを考えてみると 100÷0.25=400g という式で表せます。
このようにして、割合の公式の意味を考えてみましょう。
3人で分ける場合
等分すると 3分の1ずつ で 1÷3=0.333・・・ と割り切れない数になりますね。
50%、25%、25% という分け方も出来ます。
いろいろな分け方を考えて割合の意味を学んでいくことが出来ます。
スポーツやゲームで学ぶ
スポーツで割合を使う場面を考えてみましょう。
野球が好きなお子さんなら、バッターの打率、ピッチャーの勝率などで割合を使っています。
こちらのサイトで打率・出塁率の計算方法を解説しています。
サッカーやバスケットボールでしたら、シュートの成功率でも学ぶことが出来ます。
下のように、子どもたちでバスケットボールのシュートを入れるゲームをして、誰が一番成功率が高いかを計算すると、割合の意味が分かりやすくなります。
4人の子どもがシュートをした数とゴールをした数
いろいろなスポーツやゲームでどのように割合を使っているのか調べてみてもいいでしょう。
買い物で学ぶ

まずは、日常生活で一番身近に割合を必要とする「買い物」の場面で、お子さんと一緒に割合の意味を勉強してみましょう。
例えば、値札に「表示価格より2割値下げ」と書いてある場合、実際にいくら安くなるのか? また,消費税が8%というのは実際に定価よりいくら高くなるのか?ということから理解していけば、割合の考え方はスムーズに身に付くと思います。
値札についている税込、税別の意味
価格 1500円+税 の場合、消費税を足した値段が定価になります。消費税を加えたら実際にいくらになるか考えてみましょう。
税込 1080円 の場合 消費税はいくらになるか、消費税抜きだといくらになるか考えてみましょう。
定価 1080円 から2割引 の場合 2割引の意味 実際の値段はいくらになるか考えてみましょう。
買い物の際に、電卓を持ち歩いて、お子さんが自分で税込み価格や割引価格を計算をする習慣をつけてみてください。
日常生活の割合の意味をしっかり理解することで、算数の割合の文章題でどのような式を作ればいいのか、迷わなくなります。
割合の問題はこちら
中学受験向けの応用問題はこちら
|
新品価格 |
 |
![]()