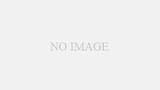応用問題が解けないのはなぜ?
「計算問題はできるのに、文章題になると手が止まってしまう」 「暗記した内容は答えられるのに、理由を説明する問題は何も書けない」
このような相談を、小学校高学年の保護者の方から多く受けます。
基本的な計算問題や一問一答式の問題は解けても、応用問題や記述問題になると全く手が出ないというお子さんは少なくありません。
実は、応用力が身につかないお子さんの多くは、普段の生活習慣や勉強法に問題があることが分かっています。中学校に進学する前の今のうちに、「考える力」を育てる習慣を身につけることが何より大切なのです。
お子さんにこんな様子はありませんか?
次の項目について、お子さんに当てはまることがないか考えてみてください。
1. 見通しを持って勉強できているか?
「今日はどのくらい勉強すればいいの?」と毎回聞いてくる、テストまでにどんな準備が必要か自分で考えられない、といった様子はありませんか。
自分でどのくらい勉強すれば宿題が終わるのか、テストでいい点数を取れるのか、こうしたことを自分で考えることができないと、学習に対しての応用力はつきません。
高学年になったら、少しずつ自分で学習の見通しを立てる練習が必要です。
2. 分からない問題があった時、自分で調べることができるか?
解答を見てマルつけをするだけ、答えを写すだけで終わっていませんか。
分からない問題に出会ったとき、「教えて」とすぐに頼るのではなく、教科書を見返したり、ノートを確認したりする習慣があるかどうかが重要です。
自分で調べる力がないと、できない問題はいつまでもできるようになりません。
3. どうしてそうなるか、理由を考えられるか?
「答えは分かるけど、どうしてそうなるかは説明できない」という状態では、応用力はつきません。
漠然と答えを暗記しているだけでは、問題の出され方が変わったときに対応できなくなります。常に「なぜそうなるのか」を考える習慣が大切なのです。
4. 教材や宿題の管理ができているか?
学校の宿題や持ち物、提出物などを、すべて保護者の方が管理していませんか。
他人任せにしていると、物事を整理する能力が育ちません。高学年になったら、少しずつ自分で管理する練習を始めることが大切です。
改善のための具体的な方法
当てはまることがあれば、次のように改善することを考えてみてください。
1. 1週間単位で学習計画を自分で作って実行させる
最初は保護者の方と一緒に計画を立ててもよいでしょう。
勉強する内容を見て、どのくらいの時間をかければ終わるか考えるようにします。問題集などは1日何ページやれば終わるかを自分で考えるようにする習慣をつけることが大切です。
慣れてきたら、週末に翌週の予定を自分で立てさせてみましょう。計画通りにいかなかったときは、何が原因だったかを一緒に振り返ることも重要です。
小学生向けの学習計画テンプレートはこちらでダウンロードできます。

2. 解答をじっくり見て、なぜそうなるか考える勉強をさせる
問題集の量をこなしていれば、勉強できていると思っていませんか。
大切なのは量ではなく、しっかり自分で理解できているかどうかです。間違えた問題は、解答を見てどこで間違えたのか、正しい解き方はどうなのかを確認するようにしてください。
「分かったつもり」で終わらせず、もう一度同じ問題を解き直してみることをおすすめします。
3. 常に理由を考えて答えさせるようにする
普段の学習だけでなく、日常生活でも理由を考える習慣が大切です。
例えば、「今日の夕飯は何がいい?」と聞くだけでなく、「どうしてそれが食べたいの?」と理由も尋ねてみましょう。ニュースを見たときに「どう思う?」と意見を聞いてみるのも効果的です。
こうした日々の積み重ねが、記述問題で自分の考えを書く力につながっていきます。
4. 学校の宿題、持ち物などは、毎日ホワイトボードなどに書いて、チェックする習慣をつける
連絡帳を見ながら、自分で明日の準備をする習慣をつけましょう。
ホワイトボードや専用のノートに、やるべきことを書き出して、終わったらチェックを入れるという方法がおすすめです。最初は保護者の方が一緒に確認してあげて、徐々に自分一人でできるようにしていきましょう。
忘れ物が減るだけでなく、自分で物事を管理する力が育っていきます。
やることを書き込むことができるホワイトボード
ソニック(Sonic) ボード リビガク マイプランボード 宿題忘れ 忘れ物をなくす アイボリー LV-4156-I 新品価格 |  |
中学校に向けて「考える力」を育てよう
応用力をつけるということは、常に自分で「考える」訓練が必要です。
中学校に進学すると、小学校よりもさらに「なぜそうなるのか」を問われる場面が増えてきます。また、自分で学習計画を立てて勉強することが求められるようになります。
今のうちから、普段の生活の中でお子さんに自分で考えさせるような習慣を身につけることが何より大切なのです。
保護者の方がすべてやってあげるのではなく、少しずつお子さんが自分でできることを増やしていく。そうした積み重ねが、中学校でも伸びる力の土台になっていきます。
焦らず、お子さんのペースに合わせて、一つずつ「考える習慣」を育てていきましょう。
お子さんが自分から学習する習慣をつける力をつけるのに参考になる本
自分から学ぶ子どもの親は知っている 小学生が勉強にハマる強み学習法 新品価格 | 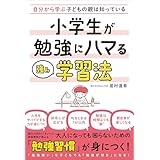 |