家庭学習を習慣づけるためには、小学生の場合は保護者の管理が不可欠になります。しかし高学年になるほど、親の意見を聞かなくなるお子さんも増えてきますし、このぐらいの年齢になって自分で学習法を確立していないようでは、成績には反映しなくなると思います。
このため、できれば小学校1年生、2年生の早い時期に、自分で進んで勉強ができる習慣を身につけることが理想です。保護者の役割は、勉強を教えることではなく、自主的に勉強できる力をつけてあげることだと思います。
お子さんの家庭学習の管理で、どのようなことができるかを書いてみますので、参考にしてみてください。
低学年の宿題管理は保護者がしっかり確認
毎日の宿題チェックが学習習慣の基本
学校で出される課題は、保護者がしっかり把握して、毎日やっているかを確認してあげましょう。
確認する項目:
- 連絡帳や配布物
- 学習用タブレットの連絡機能(GIGAスクール端末)
- 通信教育の教材
丸つけは保護者が担当する
家庭での自主学習や通信教育の教材なども、できれば丸つけまでしてあげてください。低学年のうちは、まだ正確に答え合わせが自分でできなかったり、漢字の細かい間違いなどに気づかないこともあります。
間違いの原因を一緒に考える
間違っている問題は、どうして間違えたか原因までしっかり考えましょう。このとき、正解、不正解にこだわるだけでなく、何故できなかったかをお子さんと一緒に考える習慣をつけることが大切です。
よくある原因:
- 間違った覚え方をしている
- 根本的な勉強方法に問題がある
- 苦手な部分がある
お子さんの苦手な部分を早めに把握することで、高学年での学習がスムーズになります。
タブレット学習との上手な付き合い方
GIGAスクール端末や通信教育の活用
最近では、学校でも一人一台のタブレット端末が配布され、家庭でもタブレットを使った通信教育を利用するご家庭が増えています。
タブレット学習のチェックポイント:
- 本当に理解しているか
- ただ画面を操作しているだけになっていないか
- 「今日はどんな勉強をしたの?」と声かけをする
紙とデジタルのバランスが大切
低学年のうちは鉛筆で文字を書く練習も重要です。漢字や計算は、紙に書くことで定着しやすいという研究結果もあります。デジタルと紙、両方をバランスよく使うことを心がけましょう。
タブレット学習に特化したおすすめの通信講座
低学年から使いやすいスマイルゼミでの学習もおすすめです。
教えすぎないことも大切な関わり方
答えを教えるより調べ方を教える
基本的に小学校低学年くらいでしたら、保護者が勉強を教えることもあっていいと思います。しかしお子さんに聞かれて答えられることは答えるくらいでよいと思います。
分からない漢字や言葉、社会の地名など調べれば分かることは、できるだけお子さんの力で調べさせるようにしてあげてください。低学年のうちから、辞書や図鑑で調べる習慣をつけることが、将来の学習力につながります。
達成感を感じられる工夫を
お子さんが分からないからと、家庭学習をしないで諦めてしまっているような場合は、以下のような工夫をしてみましょう。
おすすめの取り組み方
- 好きな教科の勉強から始める
- 漢字の練習や計算など取り組みやすいものを選ぶ
- 短時間でいいので「勉強した」という達成感を与える
小学校低学年の集中力は15分から20分程度と言われています。短時間でも毎日続けることが、学習習慣づくりには最も大切です。
まとめ:低学年の学習習慣が将来の学力を決める
低学年のうちに自分で勉強に取り組む習慣をつけることが、将来の学習力の土台になります。保護者の役割は、勉強を教えることではなく、お子さんが自分で学習を進められる力を育てることです。
毎日の声かけや確認を通じて、お子さんが自信を持って学習に取り組めるよう、温かく見守ってあげてください。1年生、2年生のうちに築いた学習習慣は、高学年になってからの勉強にも大きく影響します。
低学年からの学習習慣作りの参考になる本
お子さんが将来困らないように、家庭でできる「勉強習慣」の育て方を紹介した一冊です。お子さんの特性に合わせた好奇心の育て方、親の声かけや接し方、教科別の勉強法まで具体的に解説しています。変化の激しい時代を生き抜く力を育てるヒントが詰まった、低学年の保護者におすすめの書籍です。
自分から学ぶ子どもの親は知っている 小学生が勉強にハマる強み学習法 新品価格 | 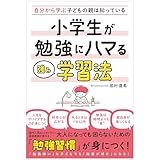 |


